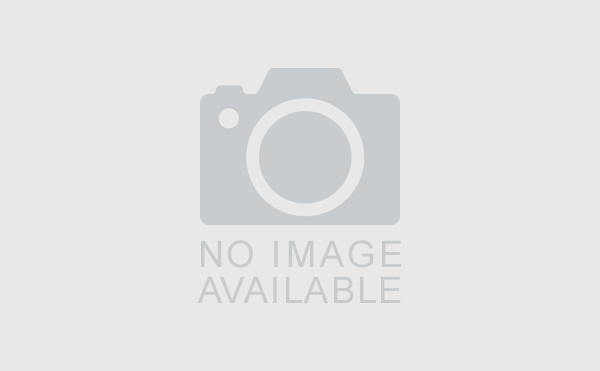もののけ姫
数年振りに映画館へ行った。コロナ禍の中、ガラガラと思いきや、残キップは少しとの表示(満員でも50%の人数制限)あり。 高校の担任であり、日本史の教師だった網野善彦先生の著書をコロナ禍の中に読み、関連事項を検索していると、”網野史観”という言葉と共にジブリ映画「もののけ姫」がでてきた。しばらくテレビでの放映を期待したが、たまたま近くで上映されることを知り、足を運んだ。時代設定が室町で、今だヤマト政権に征服されていない東北北部・蝦夷の村の若者が主人公で、呪いを解くため、西の国へシシガミを探しに旅に出る。タタラ製鉄を生業にする村民とヤマト政権下の武士の一団と山の神々との間で繰り広げられる闘いに巻き込まれながらストリーは展開する。映画の中に描写される村々の様子や市場での人々の様子が中世の絵巻物や聖絵などに基づいて正確に描かれていた。宮崎駿監督のテーマ性を強く含んだ映画であり、”網野史観”に基づいて製作されたと評されている。二人の対談の記録を読むと、室町時代が日本の転換期であったと認識を二人とも共有していることが分かる。室町以前の日本人は自由で平等な生活を送っていたのか?